SNSマーケティングの基礎|主要プラットフォームの特徴と初心者が押さえるべきポイント
- 2025.05.01
- マーケティング
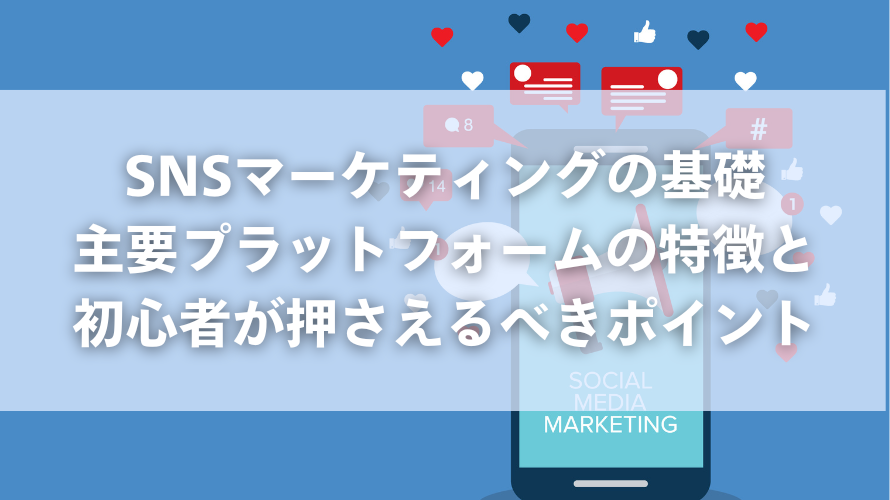
どうも、小川です!
最近は
ビジネスでもSNSを活用するのが
当たり前になってきましたよね。
「Instagramを始めてみたけど
どう投稿したらいいのかわからない…」
「X(旧Twitter)って
企業アカウントだとどう使えばいいの?」
そんなふうに悩んでいる方も
実は少なくありません。
SNSマーケティングは
ただ投稿するだけでは
成果につながりにくいもの。
プラットフォームごとの特性や
ユーザー層を理解した上で
自社に合った活用法を
見つけることが大切です。
この記事では
初心者の方でもわかるように
主要SNSの特徴や選び方を
わかりやすく解説していきます!
SNSマーケティングとは?

SNSマーケティングとは
InstagramやX、TikTokなどの
SNSを活用して
・商品の認知拡大
・ブランドイメージの構築
・ファン獲得
・購買促進
などを目指すマーケティング活動です。
SNSは無料で始められるうえ
ユーザーとの距離が近く
双方向のコミュニケーションが可能。
拡散力の強さも魅力で
うまく活用すれば企業規模にかかわらず
大きな効果が期待できます。
SNSマーケティングにおいては
以下のような施策が代表的です。
・アカウント運用による情報発信
・SNS広告
・インフルエンサーマーケティング
・ソーシャルリスニング
・キャンペーン
これらの施策は
どのSNSを使うかによって相性が変わります。
たとえば
・ビジュアル重視のキャンペーンにはInstagram
・速報性が求められる情報発信にはX
・クーポン施策やリピーター施策にはLINE
といった具合に
目的に応じた選定が成果に直結します。
そこで次は
主要なプラットフォームごとの特徴を
見ていきましょう!
主要プラットフォームの特徴と使い分け

SNSマーケティングを
効果的に行うためには
まずそれぞれのSNSの特性を
知ることが重要です。
「とりあえず全部始めてみる」ではなく
目的や発信したい内容、
自社のリソースに合ったSNSを選ぶことで
より成果につながりやすくなります。
ここでは
主要な5つのプラットフォームについて
それぞれの強みや向いている活用方法を
ご紹介していきます。
【Instagram】
| アクティブユーザー数 | 3,300万人 |
| メインユーザー | 10代後半〜30代前半の若年層 |
| 強み | ビジュアル重視のコンテンツが得意ショッピング 機能を活用したEC連携も可能 |
| 主な機能 | フィード投稿 ストーリーズ リール(短尺動画) ショッピング機能(商品タグ付け) インサイト(ユーザー分析) |
ビジュアルで魅せたいなら
Instagramがおすすめです!
写真や動画で見せることが
得意なInstagramは
ビジュアル映えする商材との
相性が抜群。
例えば以下のような
サービスと親和性があります。
・アパレル
・美容
・ライフスタイル
・インテリア
・旅行
・グルメ など
また「世界観づくり」がしやすいため
ブランドイメージの訴求や
ファン化にも向いているのが特長。
さらに
ショッピング機能で
ECサイトと連携できるため
購買につなげやすいのもいいですね。
Meta社の広告配信機能により
精度の高いターゲティング広告も可能です。
【X(旧Twitter)】
| アクティブユーザー数 | 6,658万人 |
| メインユーザー | 20〜30代 |
| 強み | リアルタイム性と拡散力が高い ユーザーとの双方向コミュニケーションも活発 |
| 主な機能 | ポスト リプライ リポスト スペース(音声チャット) ハッシュタグキャンペーン |
リアルタイムで話題をつくりたいなら
Xがおすすめ!
速報性やトレンドとの親和性が高いXは
ニュース、エンタメ、キャンペーンなどとの
相性が◎。
ハッシュタグやトレンドワードを
活用した拡散がしやすく
特に「一気に話題にしたい」
タイミングには非常に有効です。
ユーザーとの距離が近く
リプライや引用ポストによるやり取りで
コミュニティ感も生まれやすい特長があります。
【Facebook】
| アクティブユーザー数 | 2,600万人 |
| メインユーザー | 30代以上の男性 |
| 強み | 実名登録による信頼性と詳細なターゲティングが可能 BtoBや高額商品のマーケティング向き |
| 主な機能 | ビジネスページ グループ機能 イベント作成 広告ターゲティング(年齢、性別、興味関心など) Facebookインサイト(分析ツール) |
信頼感を重視したいビジネスなら
Facebookを活用しましょう。
実名登録制のためユーザーの信頼性が高く
ビジネス寄りの発信に強いSNSです。
30代以上のユーザー層が多く
BtoB商材や高額サービスとの相性も良好。
実名登録によって
ユーザー情報の確度が高いことで
広告配信のターゲティング精度も高くなるため
リード獲得や顧客との関係強化に使えます。
また、海外ユーザーも多いため
グローバル展開を視野に入れる企業にも
おすすめです。
【LINE】
| アクティブユーザー数 | 9,200万人 |
| メインユーザー | 全年齢(特に30代〜50代のユーザーの利用率が高い) |
| 強み | 国内最大のユーザー数を誇る クローズドなコミュニケーションが可能 |
| 主な機能 | LINE公式アカウント(メッセージ配信) クーポン発行ショップカード(ポイントカード機能) リッチメッセージ(画像付きメッセージ) セグメント配信(ユーザー属性に応じた配信) |
リピーター育成やクーポン施策なら
LINEが向いています!
日本国内の利用率が最も高く
「LINEだけは使っている」
という層にもリーチできるSNSです。
メッセージ配信の到達率が高く
クーポンやポイントカード、
ショップカードなど
販促施策との親和性が高いのが特長。
メルマガ感覚で配信できるので
リピート促進やユーザーとの距離感を
縮めたい企業にぴったりです。
【TikTok】
| アクティブユーザー数 | 1,700万人 |
| メインユーザー | 10代〜30代の若年層 |
| 強み | 短尺動画によるエンタメ性の高いコンテンツが特徴 バズを狙ったプロモーションやインフルエンサーマーケティングに適している |
| 主な機能 | ショート動画投稿 ライブ配信 デュエット・ステッチ(他ユーザーとのコラボ) TikTok広告(インフィード広告、ブランドチャレンジなど) TikTokインサイト(分析ツール) |
若年層をターゲットにしたビジネスなら
TikTokがおすすめ!
10〜20代のユーザーが中心で
ショート動画による訴求力が
とても高いSNSです。
動画広告は
スマホの全画面を活用する形式が多く
視覚的な没入感が強いため
ブランドや商品の印象を
深く残しやすいのが魅力。
バズが起こりやすく
・エンタメ
・美容
・ファッション
・アプリ系 など
との相性が抜群です。
SNSプラットフォームを選ぶ時のポイント
SNSを選ぶときに大切なのは
「ターゲット層の明確化」です。
誰に届けたいのかによって
選ぶべきSNSは変わります。
次に
自社が発信しやすいコンテンツ形式
(テキスト/画像/動画)を考慮すること。
無理して動画を作るより
得意な形から始める方が
継続しやすくなります。
そして、一度に全部やろうとせず
まずは1〜2つの媒体に絞って運用し
慣れてきたら広げていくのがおすすめですよ!
まとめ
SNSは
無料で始められる便利なツールですが
成果を出すには
「選び方」と「使い方」が重要です。
この記事で紹介した各SNSの特徴をもとに
自社にぴったり合うものを選んで
無理なくスタートしてみてくださいね。
最初の一歩を踏み出せば
必ず見えてくる景色があります。
焦らず、一つずつ。
まずは「知ること」から始めていきましょう!
SNSマーケティングを成功させる
ポイントを解説した記事もあるので
併せて見てみてくださいね!
SNSマーケティングを成功させるポイントとは
【BMPは経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象スクールです!】
BMPは
Webマーケティングを幅広く学べる
カリキュラムを提供している
オンラインスクールです。
マーケティングの基礎や
SEO、Web広告運用、
それぞれの施策のPDCAまで学べるので
実務ですぐ使えるスキルが身につきますよ!
「自分のビジネスに活かしたい」
「副業・フリーランスとして稼ぎたい」など
興味のある方は
ぜひお気軽にお問い合わせください。
1Dayの無料体験授業などもしているので
参加してみてくださいね!
詳しくはこちら
PS.
弊社は普段リモートワークで全員バラバラで稼働していますが、
先週は久々に大阪本社オフィスにスタッフが集結。
2年半の産休育休から復活したメンバーや、
ちょうど誕生日を迎えた最近入社した大分在住スタッフなど、
色々なタイミングが重なったので夜はみんなで食事へ。
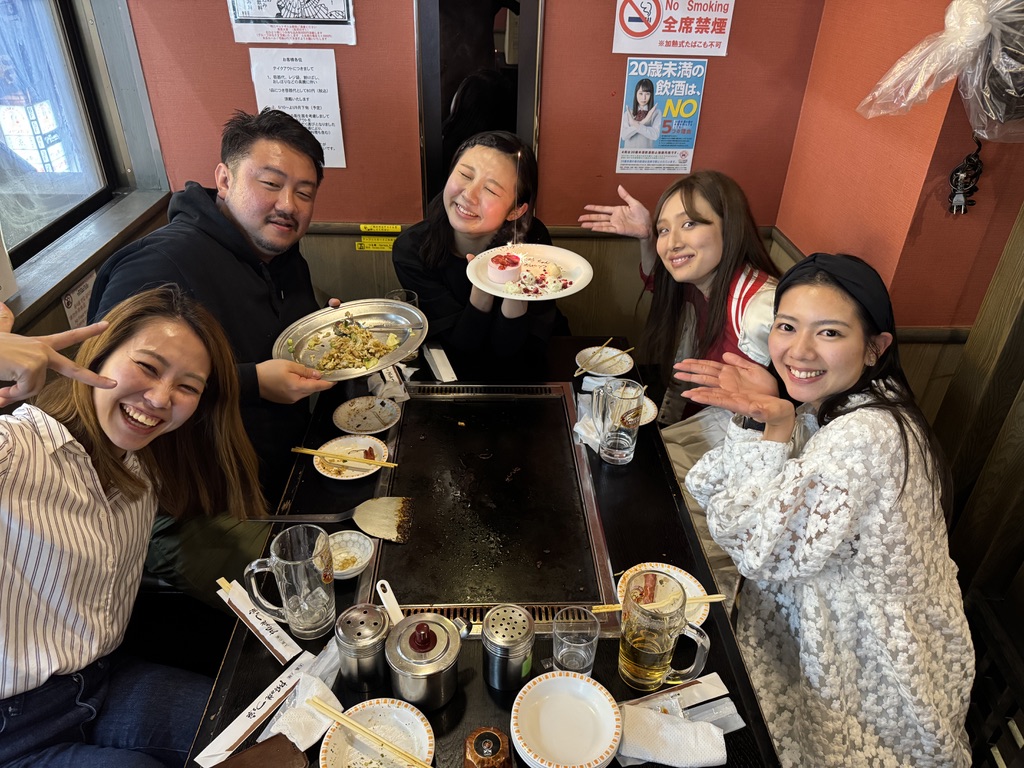

懇親会の後は以前よく行っていた、
生バンドが演奏してくれるカラオケ「BAN × KARA」へ。


ブレイクし過ぎて手に負えないスタッフ達。楽しそうで何より😏 pic.twitter.com/Ph9TMrYlGc
— 小川佳祐@BREAKな社長 (@Break_ogawa) April 26, 2025
ほぼ初対面のメンバーばかりでしたが、
それぞれ個性は強烈だけどみんな根っこの部分が似ているので、
すぐに打ち解けて騒いでました。笑
採用の際に「企業理念への理解と価値観の合致」を何よりも大切にしているからこそ、
リモートで離れていても一体感のある組織創りができているのかな?と、
おじさん(自分)は遠目で見ながらちょっとだけ自画自賛。笑
Webも大事だけど、リアルで会うのもやっぱり重要なので、
今年はまたスタッフがみんなで集まれる機会を
意図的にもっと増やしていきたいなと思いました!
小川




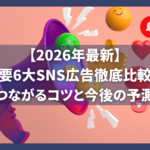
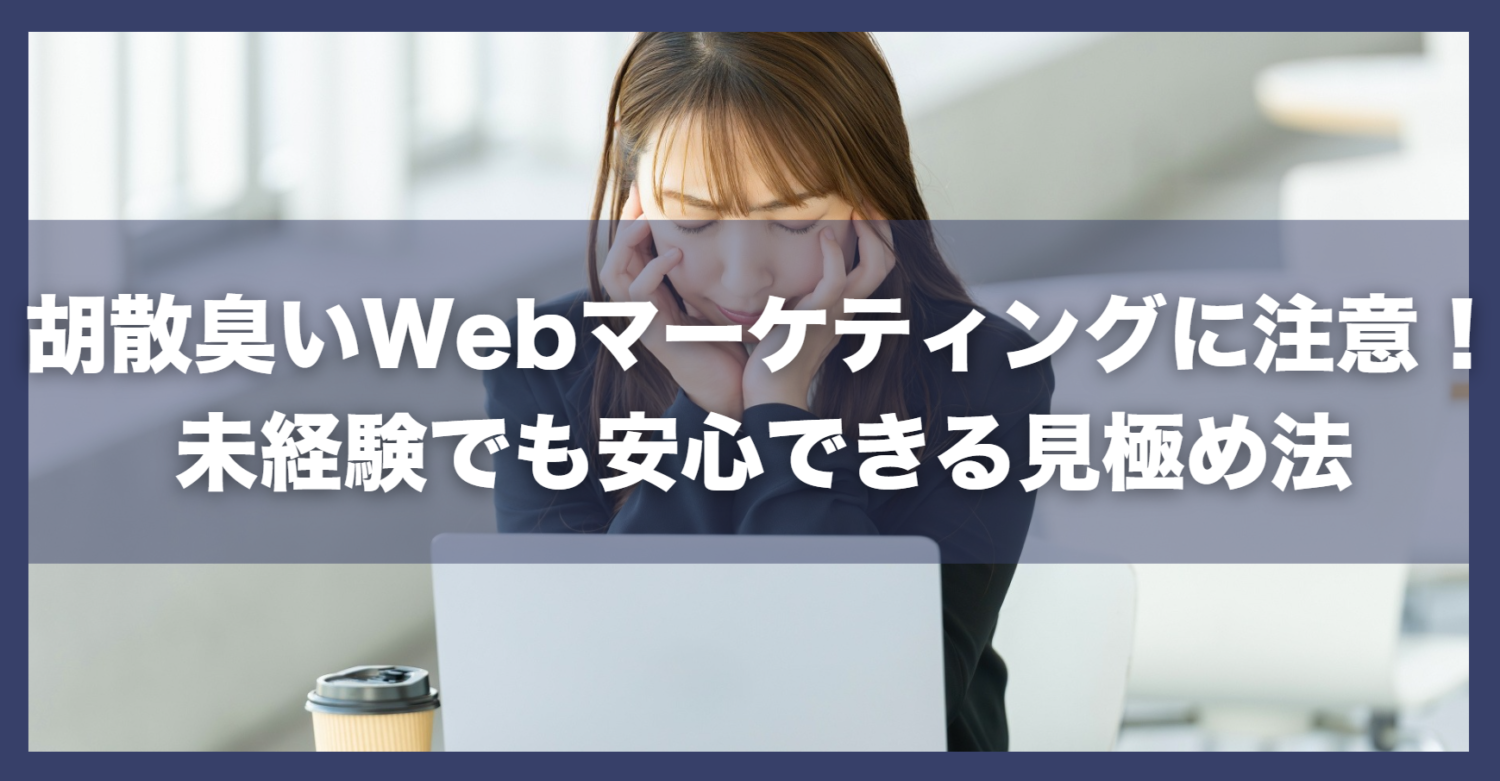

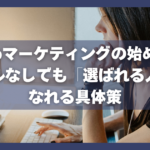
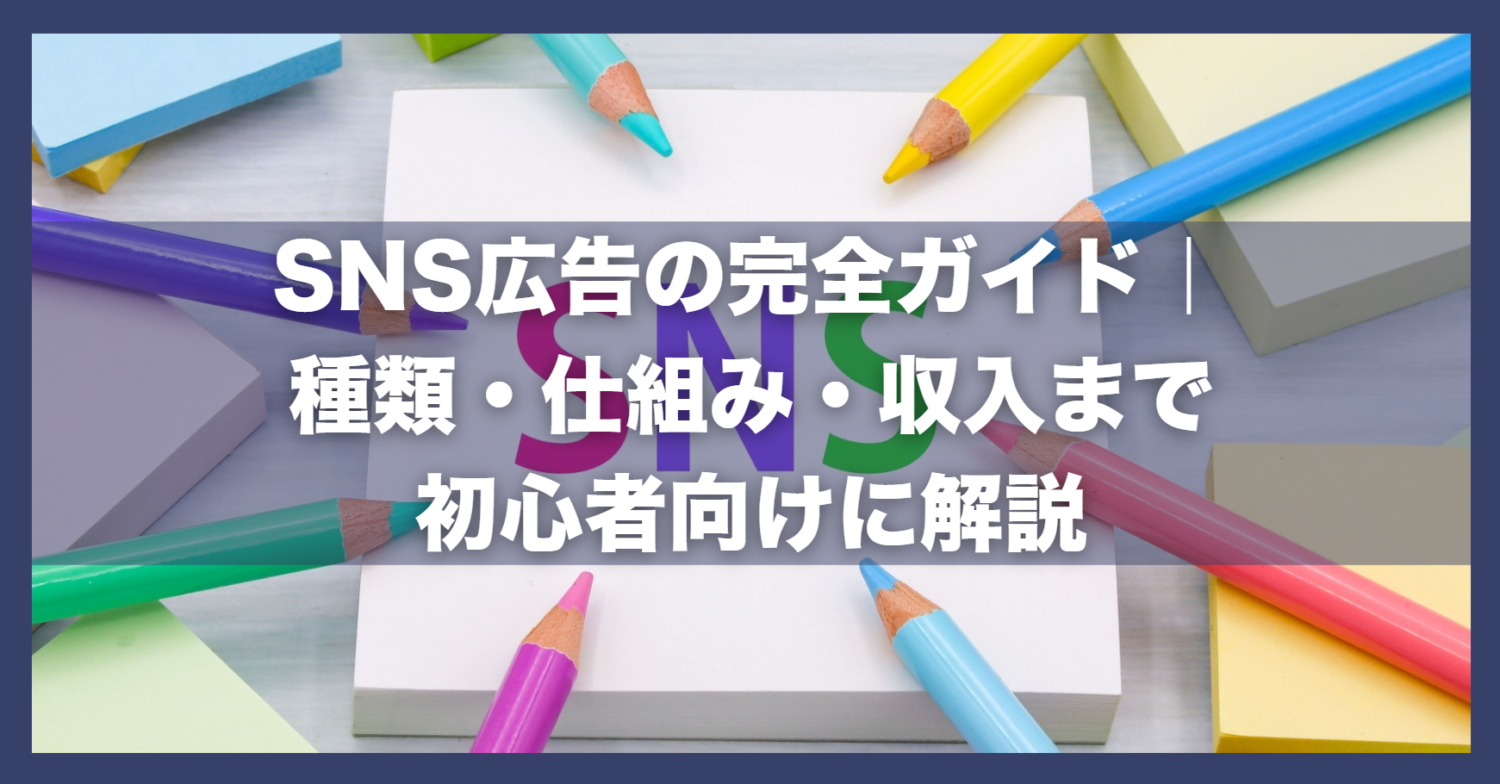
コメントを書く