「なんとなく改善」を卒業する。成果につながる“目標設定”の考え方
- 2025.09.18
- 未分類
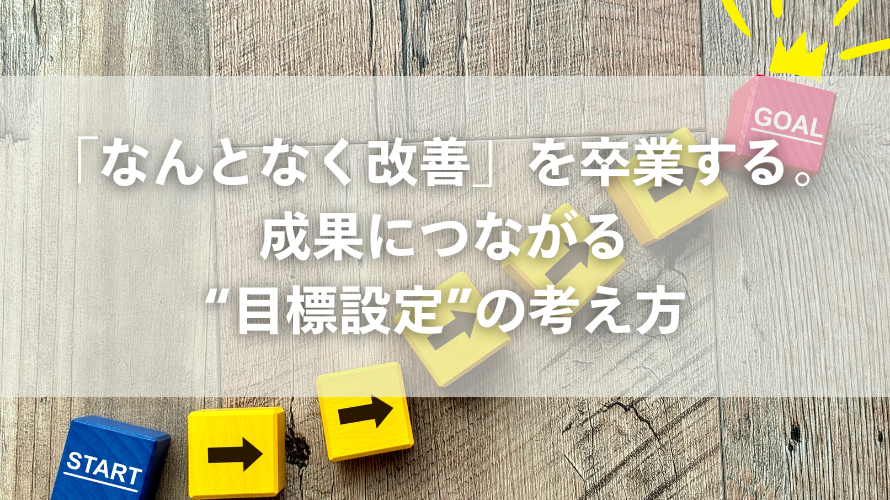
どうも!小川です。
「改善してるのに成果が出ない……」
と悩むことはありませんか?
「これ、直したほうがいいかも」
「もう少し分かりやすくできそう」
「前より良くなった気がする」
そんな風に
日々「改善」に取り組んでいるのに
思ったほど成果につながらない……。
その原因、もしかしたら
“目標”があいまいなまま改善を進めている
ことにあるかもしれません。
目の前の数字や
見た目の変化ばかりに気を取られて、
「なんのためにそれをやるのか?」
を見失ってしまうと、
改善は“自己満足”で
止まってしまうこともあります。
この記事では、
改善の精度を上げるための
“目標設定の考え方”についてお伝えします!
今まさに
「なんとなく」で動いてしまっている方には
きっとヒントになるはずです。
「目的」と「手段」がズレてしまう構造とは

改善に取り組むとき、
真っ先に浮かぶのは「施策(手段)」です。
「見出しを目立たせてみよう」
「ボタンの色を変えてみよう」
「説明文をわかりやすく書き直そう」
どれも改善の一手としては
間違っていません。
でも、もしその背景に
「なぜその施策をやるのか?」
という目的がなければ、
“とりあえず動いた”だけで
終わってしまう可能性が高くなります。
たとえば
以下のような例を考えてみましょう。
❓サイトの訪問者が少ない
→「資料請求ボタンの文言を変えよう」
一見改善に見えますが、
「そもそもボタンが見られていない」
としたら
文言を変えることが
改善につながるとは限りません。
このように
目的と手段がずれていると
せっかくの施策も
空振りに終わってしまいます。
改善がブレなくなる「目標3階層」の考え方
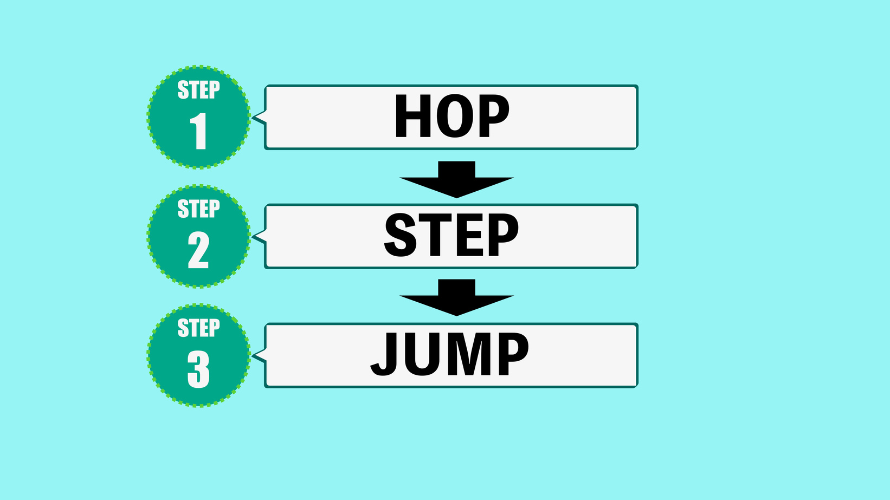
改善のアイデアを思いつくのは簡単です。
「あの言い回しがわかりにくいかも」
「デザインがちょっとごちゃついてるかも」
など、感覚ベースで気づけることは
たくさんあります。
でも、それが本当に悪い原因なのか?
どの数字にどんな変化を起こすための改善なのか?
と立ち止まって考えられているケースは
実はそれほど多くありません。
改善を「感覚」ではなく
「構造」で捉えるためには
目標と施策をきちんとつなぐ
“設計の視点”が必要です。
そこで役立つのが
「目標を3つの階層で捉える」
という考え方です。
こういう時、どう考える?|例:「資料請求を増やしたい」場合
たとえば、
サイトからの資料請求数を増やしたい
という目的があったとします。
「ボタンの位置を変える?」
「ページの順番を見直す?」と
いろいろなアイデアが浮かぶと思いますが
ここで一度立ち止まって、
その改善が“どこに効くか”を整理してみましょう。
👇改善の3階層はこんな構造になります
1:KGI(最終ゴール)
例:資料請求を月30件に増やす
💡最終的に達成したい成果指標(最も大きな目的)
2:KPI(中間の指標)
例:LPのCV率を2.0%→2.5%に改善する
💡KGIを構成する“途中経過”の数字
ここが変われば、KGIにも近づく!
3:施策レベル(具体的な改善案)
例:資料請求ボタンの文言を変える/ページ冒頭の説得力を強化する
💡実際に手を動かすアクション
KPIを改善するための具体策
※数値データやユーザー行動を根拠に選ぶと、効果につながりやすくなります
こうして構造で見てみると、
「とりあえず改善する」のではなく
“目的とつながった施策”を選ぶことの
重要性が見えてきます。
改善案を出すときは、
「それはKPIのどこに
影響を与える施策か?」
「そのKPIは、
本当にKGIにつながっているか?」
という視点で確認してみましょう!
改善の「順番」が自然に見えてくる状態へ
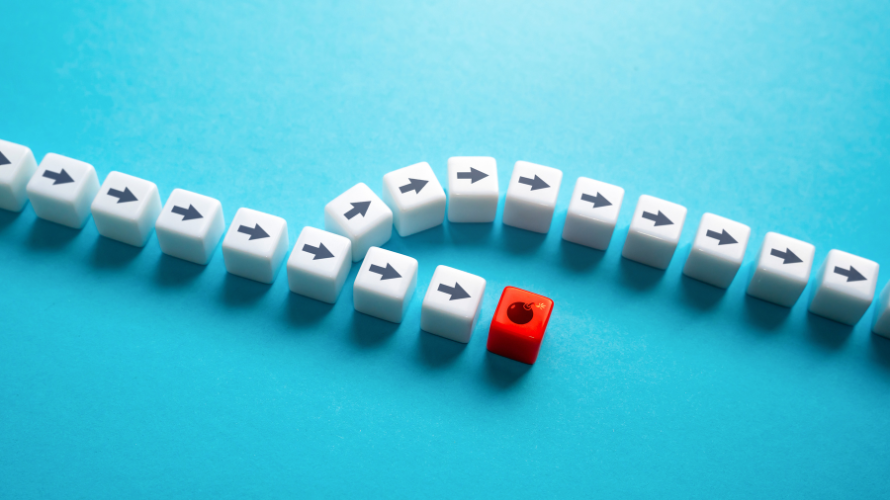
上記の3階層で目標を設計しておくと
改善施策の「優先順位」も
自然に決まりやすくなります。
たとえば、
KGI:「資料請求を月30件にする」
KPI:「LPのCV率を2.0%から2.5%にする」
施策案:「資料請求ボタンの文言を変更する」
という流れがつながっていれば、
「まずLPの導線や説得力を改善しよう」
という判断もスムーズに下せます。
一方で、ここがつながっていないと
「なぜこれをやるんだっけ?」
という状態に陥りやすく
成果の見えない改善を
延々と繰り返してしまうことにも
なりかねません。
考え方の順番を変えるだけで、改善の成果が変わる

「改善を頑張っているのに、
なかなか成果が出ない」
そんなときは、一度立ち止まって
“考え方の順番”を
見直してみることをおすすめします。
最初に「施策」から考えてしまうと、
それがどんな成果につながるかが
見えにくくなって、効果があがらず
モチベーションも下がってしまいがちです。
でも、
「何を目指しているのか(KGI)」
→「そのために必要な中間指標(KPI)」
→「その数字を改善する施策」
という順番で考えることができれば
自然と「今やるべきこと」に
集中できるようになります。
まとめ:成果につながる改善は、「目標」から始まる

改善は行動だけでなく
設計の精度によって成果が決まります。
そのためには
「思いついたからやる」のではなく
「なぜそれをやるのか?」を
明確にしたうえで動くことが欠かせません。
KGI → KPI → 施策
という3階層の構造を持って考えることで
改善のブレが減り
少ないアクションでも
しっかり成果に近づくようになります。
「なんとなく改善」を卒業し
目標から逆算する思考を
ぜひ日常の中に取り入れてみてくださいね!
【BMPは経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象スクールです!】
BMPは
Webマーケティングを
幅広く学べるオンラインスクールです。
施策を実行するだけでなく、
「何のためにやるのか?」
という目的から逆算して、
改善につなげる“考え方の力”を
実務ベースで身につけられます。
「成果が出る改善」と「空回りする改善」は
実は“考え方の順番”で大きく変わるもの。
この視点を一度身につければ、
日々の業務でも、フリーランス活動でも、
迷わず動けるスキルとして
ずっと活かせますよ!
「自分のビジネスに活かしたい」
「副業・フリーランスとして稼げる力をつけたい」
そんな方は
ぜひお気軽にお問い合わせください。
1Dayの無料体験授業も行っているので、
参加してみてくださいね!
詳しくはこちら
PS.
先週から5日ほど海外に行ってました!
今回はタイ・バンコクからベトナム・ホーチミンへ。
経営者ネットワーク「EO Kyushu」のメンバーで
ベトナム出身のルアン社長( https://x.com/RuanInose )に色々アテンドしてもらい
海外ビジネス視察ツアーをしてきました!

バンコクから車で2時間かけて
「願い事が通常よりも3倍のスピードで叶う」
と言われているピンクガネーシャに参拝に行くことに。

「BMPを通じて、より多くの人が夢を実現できるように」と、
願い事を届けるネズミに耳打ちでお願いしてきました。

ルアン社長の故郷であるベトナムでは
地元の人しか知らない超絶美味しいローカルフードを色々教えてもらいました!

ルアン社長の経営する「JV-ITホールディングス (https://jv-it.jp )」も訪問!
100人以上のベトナム人エンジニアを雇用して国内や日本の開発案件を受注しているそうで、オフィスの壁の「青色」にかなりこだわりを持っているそうです!

早稲田大学のサークルの先輩で、
大塚製薬のベトナム支社長をされている小山田さんと。
ポカリスエットをベトナム市場で販売拡大するためのマーケティング戦略をお聞きできて、かなり面白かった!

タイもベトナムもそうですが、まだまだこれから成長しそうな国々に行くと、かなり良い刺激を受けますね。
日本や自分を客観的に見直す機会になるし、残りの自分の人生を使って何を成し遂げるべきなのか、改めて考えさせられました。
現地に縁のある方々にアテンドしてもらえると、より深くその地域を知れるのでありがたいですね!
もっと沢山の繋がりを作って、色んな国に行くぞー!
小川

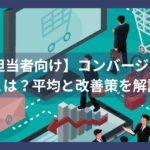
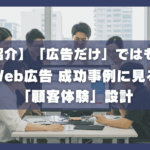

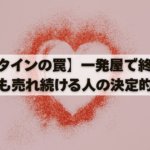
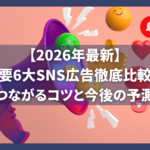
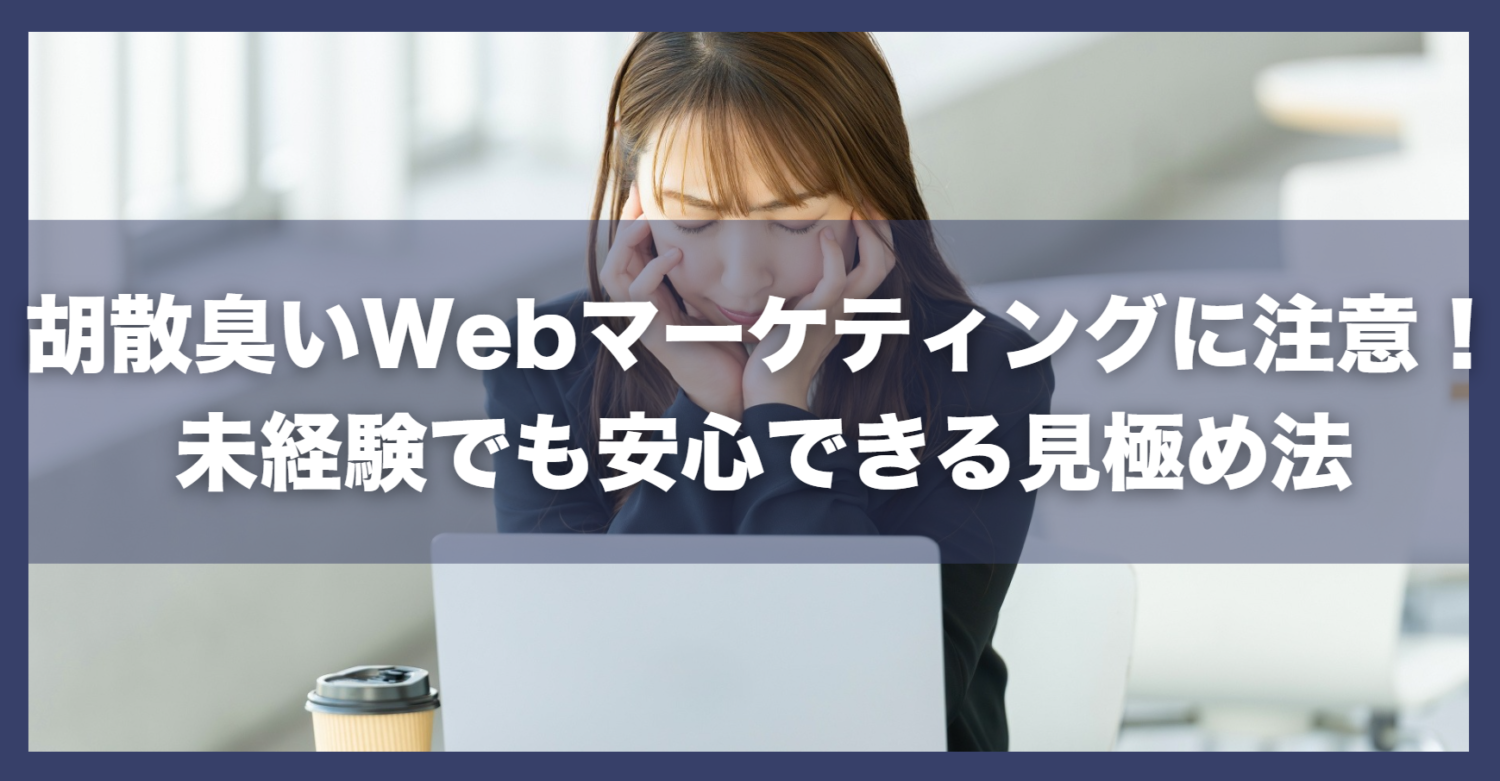

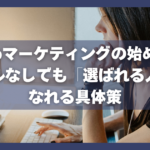
コメントを書く