AIはアイデアの相棒?マーケ脳で考えるAI活用のコツ
- 2025.08.18
- マーケティング
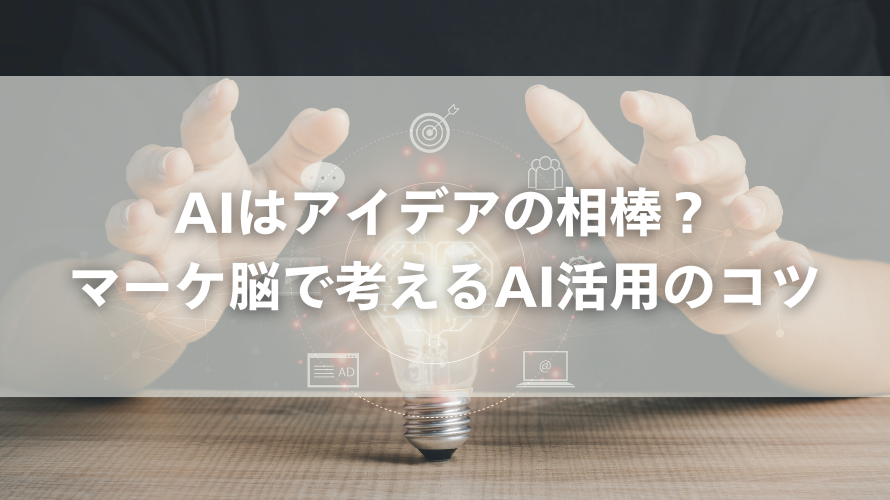
どうも、小川です!
ChatGPTや生成AIの普及で
「仕事が奪われるのでは?」
という不安を耳にすることが増えました。
確かに
同じ作業を繰り返すだけの業務や
判断が不要な単純作業は
AIに置き換わりやすい領域です。
逆に
自分で目的を設定し、戦略を描き、
最適な手段を選べる人材は
AI時代にこそ価値を高めます。
つまり、AIに指示される立場ではなく
自分で目的を決めてAIを動かせることが
これからの時代に必要な力です。
今回の記事では
この“AIを指揮できる力”を磨くために
マーケター的な思考=「マーケ脳」
をベースにしたAI活用のコツを解説します。
AIは「代替」ではなく「加速装置」

AIは便利ですが
そのまま使っても
思った通りの成果は出ません。
大事なのは、どう使うかを設計すること。
たとえば、
SNS投稿のアイデアを出すときも
「ターゲットは誰か」
「どんな印象を与えたいか」
など条件を整理してからAIに指示すると
出力は格段に質が上がります。
マーケティングでは昔から、
ツールやメディアの使い方一つで
成果が変わります。
AIも同じ。
ただの置き換えではなく
加速させるための道具として
捉えることが重要です。
AIを実務で本当に使いこなす人は、最初に
「何がしたいか」
→「それをAIでどう楽に・速くできるか」
という順番で考えます。
逆に
「AIで何ができますか?」と聞くスタンスは
主導権をAIに渡す使い方。
これはAIに代替されやすい人の発想です。
構造を持つ人ほどAIで強くなる理由

ここでいう“構造”とは
目的→戦略→戦術のように
ゴールまでの道筋を
階層的に整理できる思考のこと。
マーケ脳を持つ人は
この構造を自然に描けるため
AIへの指示も明確で具体的になります。
💡構造がある場合
| AIに「こういうターゲットに、こういう印象を与える、〇〇字程度の文章」と指示できる。 |
🌫️構造がない場合
| 「SNS投稿作って」とだけ指示し、出てきた結果に一喜一憂する。 |
結果、前者は狙った出力を得やすく、
後者はAIに振り回されやすくなります。
“質問力”と“評価力”のある人ほど
AIを強い味方にできるのです。
マーケ脳で使う!AI活用の3ステップ

マーケ脳でAI活用する
3ステップを見ていきましょう!
①目的の明確化
AI活用の出発点は「何を達成したいか」
で考えること。
「AIで何ができますか?」
ではなく
「自分は何をしたいか」
を決めるのが先です。
例えるなら、
AIは自動運転タクシーのような存在。
行き先(目的)を決めないまま走らせても
行きたい場所にはたどり着けません。
行き先が明確になって初めて
自分がハンドルを握り
AIを思い通りの方向に走らせられるんです。
②指示の構造化
目的が決まったら
それを達成するための要素を分解して
AIに伝えます。
AIは“指示された条件”の中で
最適解を探すので
条件が具体的であるほど精度が上がります。
例えばSNS投稿案を作るなら
・誰に向けて(ターゲット属性)
・どんな印象を与えたいか(トーンや雰囲気)
・何をしてほしいか(ゴール)
・制限(文字数・禁止表現など)
この4点を入れるだけでも
出力は別物になります。
これは料理に似ています。
「美味しいもの作って」よりも
「3人分・和風
30分以内で作れる・鶏肉メインの料理」
と言われた方が
相手は具体的に動けますよね。
③評価と改良
AIは“一度で完璧”を出すこともありますが
それはむしろ例外です。
出てきた結果は必ず自分の基準で評価し
足りない部分や方向性のズレを見つけて
再指示します。
このときのコツは
「何が良くて、何が足りないのか」
を明確にフィードバックすること。
例えば
「もっとカジュアルに」
「例を2つ追加」
「専門用語を減らす」など
修正点を具体的に伝えると
AIはその場で学習して精度が上がります。
マーケティングのPDCAと同じく
AIとのやりとりも
改善サイクルを回すほど成果が伸びるのです。
初心者でも怖くない!失敗を減らすAIの使い方

AI活用で失敗しやすい原因の多くは
AI任せにしてしまうこと。
まずは「これをやりたい」という
ゴールを自分で決めることが最も大事です。
ゴールがあれば
そこから逆算して必要な条件を整理し
AIに伝えるだけで
精度は大きく上がります。
さらに
出てきた結果を“鵜呑みにしない”こと。
必ず自分の目で確認し
「この部分は良い」「ここは修正」
と評価しながら使うことで
長期的に見ても
あなた自身のスキルアップにつながりますよ。
まとめると、
①ゴールを決める(AIの方向性を握る)
②条件を具体的に伝える(材料を揃える)
③出力を評価して必要な修正を指示する(改善サイクルを回す)
この3つを意識するだけで
AI活用の失敗はぐっと減ります。
まとめ

AIは代替ではなく
自分の思考を加速させるパートナー。
特に、
目的や戦略の構造を描けるマーケ脳を持つ人は
その強みを何倍にも伸ばせます。
そして、AI時代に“生き残る人”は
AIに指示される人ではなく
AIを指揮できる人です。
目的を明確にし
条件を構造化して伝え
結果を評価・改良する。
このシンプルな3ステップが
AIを単なる便利ツールから
自分の武器に変える第一歩です。
今日から、あなたの仕事や学びの中で
小さなタスクから試してみてください。
「AIに負けない」ではなく
「AIと一緒に加速する」未来が
見えてくるはずです。
【BMPは経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象スクールです!】
BMPは
Webマーケティングを幅広く学べる
カリキュラムを提供している
オンラインスクールです。
マーケティング思考を学ぶことで
生成AIを“代替”ではなく
加速装置として活かすための
ベーススキルを身につけられますよ!
「自分のビジネスに活かしたい」
「副業・フリーランスとして稼ぎたい」など
興味のある方は
ぜひお気軽にお問い合わせください。
1Dayの無料体験授業などもしているので
参加してみてくださいね!
詳しくはこちら
PS.
実は先週末から3日間、人生で初めて秋田県に行ってきました。
弊社が熊本や岐阜、大分、香川で展開している「地方創生プロジェクト」の情報を見て、
秋田市役所の方から「ぜひ秋田でもデジタル人材育成等を展開して欲しい」とオファーをいただき、ご縁を感じて秋田市に視察に行くことになりました!
秋田にはBMPの卒業生であり、現在はリモートでBMPに関わってくれてる講師がいるので、前入りして秋田市内を色々案内してもらいました!

街中のいたるところでパラソルの下でアイスを売っている「ババヘラ」って知ってました?
めちゃくちゃフレンドリーだったし、アイスも美味しかった!

秋田名物「きりたんぽ」もしっかり食べてきました!

絶対に会いたいと思っていた秋田犬とも触れ合うことができました!

夜は秋田市の方にアテンドいただき、
地元企業や進出企業の皆さんと交流。
地域の課題や想いを色々聞かせてもらえて、
とても有意義な時間でした!


今回秋田に行って、改めて感じたことが2つ。
1つ目が、地方でのDX推進において、首長の意向と意思決定が大きな影響を与えるな、という事。
秋田は知事&市長が世代交代したことで、DX化や人材育成に一気に舵を切っているのを感じました。
古い慣習を変えるのは抵抗も反発も出るので中々進まない。地方が時代の変化に適応する為に、半強制的にトップダウンで進める事も超重要だなと再認識。
そして2つ目は、「地方の課題=日本の課題」。
今回は秋田市役所にお声がけいただいて視察に来たけど、全国色々な地域を回って地元の行政職員や中小企業経営者に話を聞くと
「うちの地元は◯◯な課題があって大変だ」
と言われるけど、そのほとんどが他地域と同じ。つまり日本の地方都市の共通課題。
だからこそ、成功事例をどこかの地域で1つ作れれば、他地域でも展開可能。
3年前に熊本から始まった弊社の「地方創生プロジェクト」を通じて、地方に眠っている「価値」を掘り起こしたい、という思いがより強くなりました。
ブレイクが関わることで、自治体と連携して地場企業を中心にWebマーケティング支援やデジタル人材の育成、雇用促進に関して小さな成功事例を積み重ね、地域全体を巻き込んで経済を循環させるプロジェクトを全国に増やしたい。
より多くの方がWebマーケティングを習得して地方の魅力を発信する力を身につけてもらい、一緒に日本を地方から盛り上げていきたい。
皆さん、ぜひ力を貸してください!!!
小川

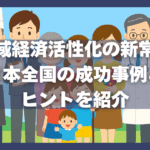
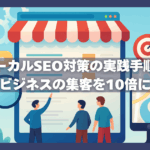

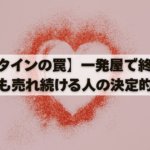
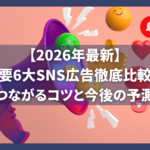
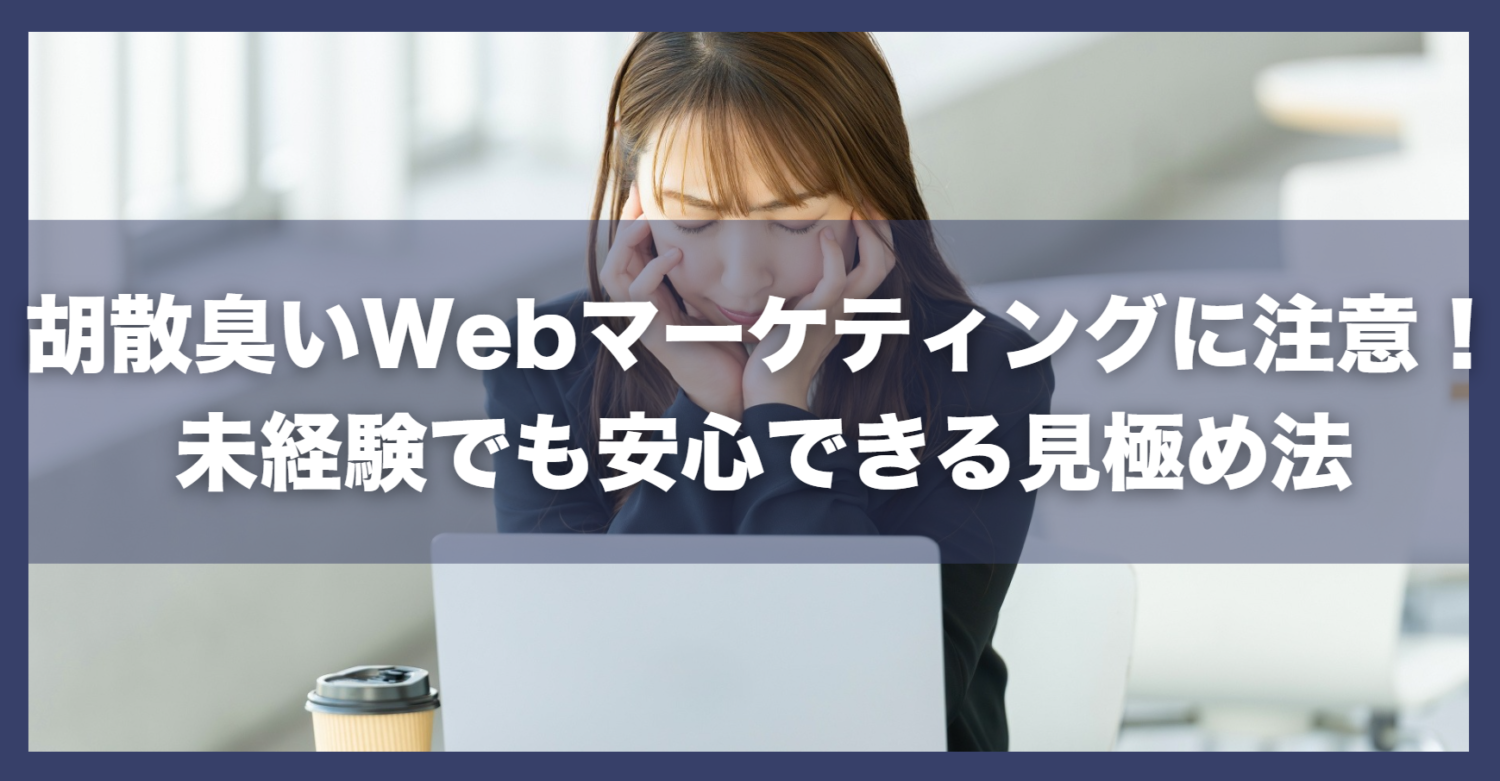

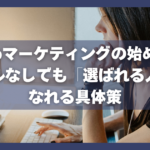
コメントを書く